自転車 イヤホン オープンイヤーを安全に使いたい方へ。
最近「自転車に乗りながらイヤホンって、やっぱり危ないの…?」と不安を感じる声が増えており、街中やサイクリングロードでも耳を塞がない“オープンイヤー型イヤホン”の利用者が目立つようになりました。
「音楽・ラジオで気分を上げたい」「ナビ音声を聞きたい」
でも、安全面や法律が心配で一歩踏み出せない…
そう感じている方も多いのではないでしょうか?
そこで本記事では、最新のオープンイヤーイヤホンの特徴だけでなく、
道路交通法、安全性、実体験レビュー、比較表までを網羅。
リアルユーザー目線のレビューとして、正直な感想もお伝えします。
読み終える頃には、あなたにとって
どのイヤホンが最適なのか?
そして
本当に安全に使えるのか?
が明確になります。
あなたの自転車ライフが、もっと快適で、もっと安全になりますように。
それでは、スタートです!✨

※街中での走行イメージ。耳を塞がないオープンイヤー型なら周囲の音を確認しながら安全に走行できます。
第1章|自転車でイヤホンを使うならオープンイヤーが安全な理由
結論から言うと、イヤホンを使いながら自転車に乗るなら、
耳を塞がない「オープンイヤー型」が最も安全で現実的な選択肢です。
自転車でイヤホンを使うときに気になるのが、「どこから違反になるのか」「罰則はどうなっているのか」というポイントだと思います。
そうした法律・ルール面については、自転車の青切符制度と違反行為の具体例で詳しく解説しています。
また、「そもそもイヤホンを使うほど通勤時間が長くてつらい…」という方は、MOVE e-Bikeで満員電車から自転車通勤に切り替える方法も参考になるはずです。
● なぜ「オープンイヤー型」が最適なのか?
自転車走行中に特に危険なのは、外部音(車・歩行者・自転車・警笛)に気づけない状態です。
一般的なカナル型イヤホンは耳を完全に塞いでしまい、音の遮断が大きく危険度が高まります。
一方、オープンイヤー型(骨伝導/耳掛け型)は、
- 鼓膜ではなく骨・空気振動で音を聴く方式
- 耳の穴を塞がず周囲の音が自然に聞こえる
- 交通状況の変化に反応しやすい
- 音楽・ナビ音声が聞けるバランス運用が可能
例えるなら、「ヘッドホンで耳を塞ぐ」のではなく、
「環境音の中に音声が重なるイメージ」です。
外の音が聞こえるので、後方車両・クラクション・歩行者の声も把握できます。
● 実際の利用シーンでのメリット
- ナビの音声案内が聞こえるので道に迷いにくい
- ロードバイクや通勤でも使用しやすい
- サングラス・ヘルメットと併用できるモデルも多い
- 長時間使用でも耳穴が痛くなりにくい
※ただし、オープンイヤーなら100%安全・完全に合法という意味ではありません。
各自治体の条例、音量調整、走行環境に合わせた自己判断が必要です。
自転車全体の安全対策や防犯面については、自転車の防犯登録をネットで済ませる方法と注意点もあわせてチェックしておくと安心です。
● 第1章まとめ
- 自転車 × イヤホンなら「オープンイヤー型」が最適
- 耳を塞がず周囲音を確保できる点が最大の安全性
- ナビ案内・音楽を安全に両立できるリアルな選択肢
第2章|自転車 × イヤホンのルールと禁止行為|自治体ごとの違いも解説
本章は公式情報をもとに整理した概要です。
「全国共通で使用が許可されている」「特定イヤホンなら完全合法」という訳ではありません。
最新情報は必ず各自治体の公式サイトをご確認ください。
● 国の規定(道路交通法)
国が定める道路交通法では、イヤホン使用を名指しで禁止していません。
しかし、以下の規定により、「安全な運転に支障が出る状態」は違反となります。
● 道路交通法 第70条「安全運転の義務」
周囲の交通状況を把握し、危険を防止するよう適切な速度と方法で運転しなければならない。
● イヤホン規制は「自治体ごと」に異なる
日本では自治体ごとに安全条例・判断基準があり、地域によって取締り内容や重点項目が異なります。
特に
「大音量で周囲の音が聞こえない状態」
と判断された場合は指導・罰則の可能性があります。
| 例 | 内容(要点) |
|---|---|
| 東京都 | 安全な運転に支障を及ぼす行為を禁止 |
| 大阪府 | 周囲の音が聞き取れない状態を禁止 |
| 愛知県 | 運転に支障を及ぼす恐れのある使用は不可 |
自転車 イヤホン オープンイヤーの法律確認に役立つ公式リンク
自転車とイヤホンに関する法律・条例は、全国一律ではなく自治体によって判断基準が異なる場合があります。
最新の正確な情報は、必ず公的機関でご確認ください。
▼ 法律・交通安全に関する公式サイト
※本記事は上記公的機関の情報をもとに編集・執筆していますが、条例変更等により内容が変わる可能性があります。
最新の公式情報をご自身でもご確認ください。
第3章|オープンイヤー型イヤホンを自転車で使ってみた実体験レビュー
ここでは、筆者が実際にオープンイヤー型イヤホンを装着し、街中・サイクリングロード・住宅街で試した体験レビューを紹介します。
あくまで個人の体験ではありますが、リアルな使用感を知りたい方に参考になるよう、細かい視点でお伝えします。
● 使用環境・条件
| 使用モデル | (例)Shokz OpenRun Pro |
| 走行エリア | (例)都内サイクリングロード・幹線道路・住宅街 |
| 走行状況 | (例)時速14〜24km、昼間、晴れ |
| 音量設定 | (例)スマホ音量30〜40%設定 |
● 実際に使ってみたリアルな感想
- 道路の「車の走行音」「自転車ベル」「歩行者の声」が普通に聞こえた
- 「音楽」は背景的に聞こえ、主役はあくまで“外音”という印象
- 音量を上げすぎると交通音が聞こえにくくなるため調整が重要
- 耳が痛くならず長時間走行でもストレスがなかった
- ナビ案内が正確に聞こえるためストップ回数が減った
※気になった点(デメリット)
- 風が強い日・車通りが多い道路では音が聞こえにくい
- 音質の迫力はカナル型イヤホンに劣る
- 街中だと安全性を配慮して音量の調整が必須
● 総合評価(5段階)
| 安全性 | ★★★★★ |
| 快適性 | ★★★★☆ |
| 音質 | ★★★☆☆ |
● 第3章まとめ
- 確かに外音が聞こえるため、安全面の不安はかなり軽減
- 音楽というより「必要情報の取得目的」の使用が向いている
- 風の強い日・交通量の多い道路では音量に注意が必要
第4章|自転車向けおすすめオープンイヤーイヤホン5選|用途別に厳選
ここからは、自転車 イヤホン オープンイヤーの中から、自転車走行との相性と安全性を重視して選んだ5モデルを紹介します。
それぞれの特徴と、自転車ユーザーにとってのメリットをまとめました。
イヤホンだけでなく、「そもそも通勤スタイルそのものを変えたい」という方は、
満員電車から自転車・電動アシスト通勤へ乗り換えるための体験談とノウハウをまとめた
MOVE e-Bikeで通勤ストレスを減らすための完全ガイド
も、あわせてチェックしてみてください。
① Shokz OpenRun Pro|骨伝導の定番・安定感重視
骨伝導イヤホンといえばまず候補に挙がる定番モデル。
耳を塞がずに音を伝えるので、車や自転車の走行音を聞き取りながら音声案内を使いたい人に最適です。
- 耳を完全に塞がない骨伝導タイプ
- 長時間装着でも耳が痛くなりにくい軽量設計
- 雨や汗にも強く、通勤・通学ライド向き
② Sony LinkBuds WF-L900|耳を開放したままの独特な構造
ドーナツ状のユニークなデザインで、耳を塞がずに音楽や音声を楽しめるソニーの人気モデル。
街中でも周囲の音がしっかり聞こえるため、自転車利用と相性の良いオープンスタイルです。
- 独特なリング型ドライバーで外音が自然に聞こえる
- 小型・軽量で常時装着しやすい
- 音質とデザイン性の両立を求める人向け
③ Anker Soundcore V20i|コスパ重視のオープンイヤー
手の届きやすい価格帯ながら、IP55防塵防水やマルチポイント接続など、日常使いに嬉しい機能を備えたモデル。
初めてのオープンイヤーイヤホンにも選びやすい1台です。
- IP55防塵防水で汗やホコリにも強い
- マルチポイント対応でスマホ+PCなど同時待ち受け
- 価格と機能のバランスがよく、入門機に最適
④ UGREEN オープンイヤー型イヤホン|高音質と装着感のバランス型
UGREENらしいコスパの良さと、18mmチタンドライバーによるクリアな音質が特徴のモデル。
自転車だけでなく、リモートワークや普段使いとの兼用にも向いています。
- 18mmチタンドライバーでHi-Fiサウンド
- IPX5防水で突然の雨や汗にも対応
- 耳掛けスタイルで安定した装着感
⑤ SOUNDPEATS PearlClip Pro|デザイン重視のクリップ型
アクセサリー感覚で使えるクリップタイプのオープンイヤー。
ファッション性と機能性を両立させたい人、自転車以外でもおしゃれに使いたい人に向いています。
- 耳に挟むような独特のクリップ構造
- 通話品質と音質のバランスが良く、マルチユース向き
- デザイン性が高く、普段使いもしやすい
※リンク先はAmazon.co.jpの商品ページです。価格や在庫状況は日々変動するため、最新情報は各商品ページでご確認ください。
第5章|失敗しないオープンイヤーイヤホンの選び方|自転車利用で大事なポイント
自転車でイヤホンを使うなら、耳を塞がない「オープンイヤー型イヤホン」が安全面で最有力候補です。
ただし、何となく人気モデルを選んでしまうと「走行中にズレる」「バッテリーが持たない」「雨の日に不安」など、後悔ポイントも出てきます。
ここでは、自転車 イヤホン オープンイヤーで失敗しないためのチェックポイントを、分かりやすく整理しました。
自転車 イヤホン オープンイヤーで失敗しない5つのチェックポイント
-
耳を塞がない設計か?
→ 骨伝導タイプ or 耳掛け型の「オープンイヤー設計」を選びましょう。
イヤーピースで耳穴をふさぐカナル型は、自転車用途では基本的にNGです。 -
走行時に外れないか?フィット感は十分か?
→ 「ジョギング対応」「スポーツ向け」などの表記があるモデルなら、
頭を振ってもズレにくく、自転車走行時も安定しやすいです。 -
防水・防汗性能があるか?
→ ちょっとした雨や汗を想定すると、IPX4以上が安心ライン。
通勤・通学で毎日使うなら、IPX5〜IPX7クラスも検討の価値ありです。 -
バッテリーが実用レベルか?
→ 片道30〜40分の通勤で使うなら、再生時間5時間以上は欲しいところ。
休日ライドやロングライドも想定するなら、8〜10時間クラスだと安心感が違います。 -
音量調整が細かくできるか?
→ 自転車では「小さめの音量でも聞き取りやすい設計」が重要です。
最小音量でも音が大きすぎるモデルは、周囲の音を聞き取りにくくなるので要注意です。
※「最高音質モデル」=「安全」というわけではありません。
自転車用途では、音楽の迫力よりも「周囲の音をどれだけ自然に聞き取れるか」が最重要です。
迷ったら、音質よりも安全性・装着安定性・防水性能を優先して選びましょう。
通勤・子どもの送迎・週末サイクリング…シーン別に優先すべきポイント
同じオープンイヤーイヤホンでも、「いつ・どんな乗り方をするか」でベストなモデルは変わります。
-
平日通勤・通学メイン
→ 軽量でフィット感が良く、バッテリー5〜8時間・IPX4以上が目安。
電車や徒歩でも使うなら、デザイン性やマイク性能もチェックしておくと便利です。 -
子どもの送迎・買い物など、短時間の街乗り
→ とにかく周囲の音がしっかり聞こえることが最優先。
音量を上げなくても聞き取りやすいモデルを選ぶと、安心感が違います。 -
週末サイクリング・ロングライド
→ 長時間バッテリー(8時間以上)と装着安定性がカギ。
メガネやサングラスとの相性も確認しておくと、長距離でもストレスが少なくなります。
具体的なモデル選びは、
▷ 第4章|自転車向けおすすめオープンイヤーイヤホン5選
で紹介している「編集部おすすめモデル」と照らし合わせながらチェックしてみてください。
あわせて読みたい
▷ ネットでできる自転車防犯登録ガイド|オンライン手続きの流れと注意点
自転車 イヤホン オープンイヤーを検討するタイミングは、
自転車そのものの防犯対策を見直すベストタイミングでもあります。
「もしものトラブル」に備えて、防犯登録や鍵の強化も一緒にチェックしておきましょう。
第6章|自転車でオープンイヤーイヤホンを安全に使うためのチェックリスト
特にオープンイヤー型は安全性と相性がよいものの、使い方を誤るとリスクが残ります。
ここでは、自転車 イヤホン オープンイヤーを毎日安心して使用するための判断基準を具体的にまとめました。
1. 出発前に必ずチェックするべき10項目
- イヤホンはオープンイヤー型または片耳である
- 音量は低く設定し、車・自転車のベル・歩行者の声が明確に聞こえる
- 周囲が騒がしい状況でも“音量を上げすぎない”意識ができている
- 交通量の多い道路・交差点に入る前に音量をさらに下げる癖がある
- 風切り音で聞こえづらいときは、速度を落とすか安全な場所に停車できる
- 走行中の「ながらスマホ」「地図の操作」は絶対にしない
- 雨天時・夜間などの視認性が低いときは、利用を控える判断ができる
- イヤホンがズレたらすぐに調整せず、安全な場所へ停車できる
- 「音楽を楽しむ」よりもナビ・通知など最小限の利用に絞れている
- 緊急車両(救急車・消防車・パトカー)に即反応できる
2. 次の状況では“イヤホンを一時的に止める or 外す”のが安全
自転車 × イヤホン × オープンイヤーの組み合わせでも、以下のシーンでは事故リスクが急上昇します。
- 大型車(トラック・バス)が多い道路に入るとき
- 坂道でスピードが出ているとき(風切り音が増加)
- 見通しの悪い交差点やスクールゾーンを走行するとき
- 強風・突風で風切り音が急に増えたとき
- 急に雨が強くなり、視界が悪化したとき
- 夕方〜夜間で交通量が増える時間帯に走るとき
- 集中力が低下している・疲労があるとき
※自転車の事故データでは、「周囲の音に気づくのが遅れた」ことが原因になるケースが非常に多いと言われています。
危険を感じた瞬間にイヤホンの再生停止 or 外す判断ができるかどうかが安全の分かれ道になります。
3. 「聞こえているつもり」が最も危険。事故を避けるための行動原則
- 聞こえにくい=音量を上げるではなく、まず速度を落とす
- イヤホンの調整やモード切替は、必ず停車してから行う
- ナビ音声は「案内前にピコン音が鳴る設定」にしておくと安全性UP
- 交差点では“一時的にミュート”するだけで事故リスクが大幅低下
- イヤホンの“外音取り込み機能”より、オープンイヤーのほうが安全
自治体によってルールが異なるため、
▷ 第2章|自転車×イヤホンの法律と自治体ルールを確認する
も必ずチェックし、「ルール」と「マナー」両方から安全運転を徹底しましょう。
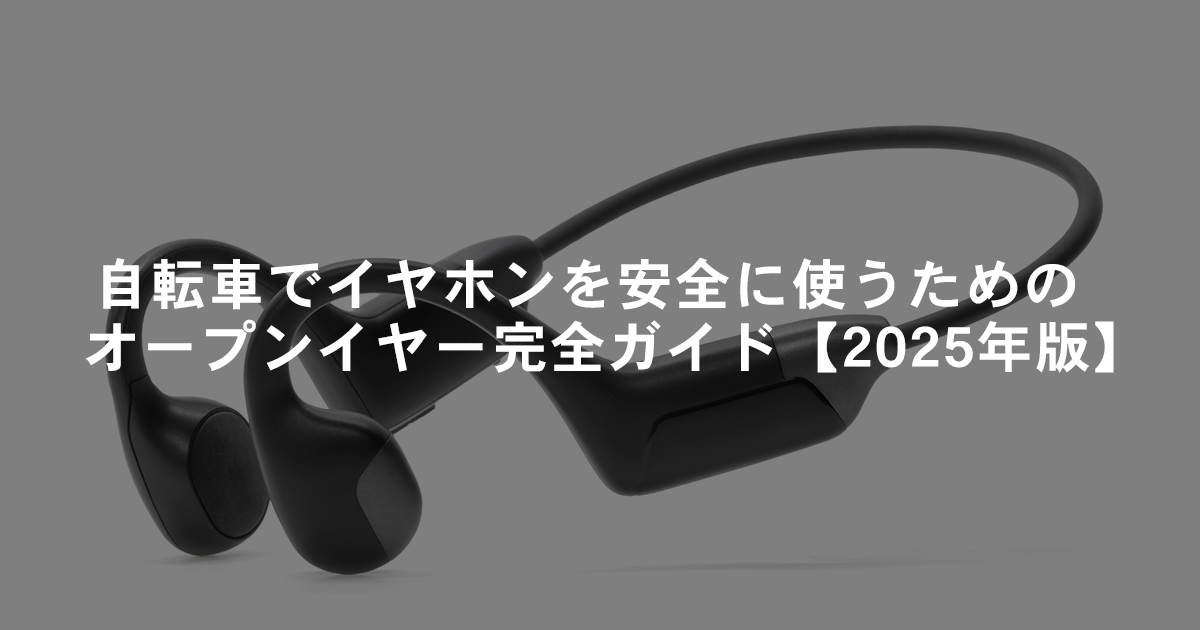


コメント